記事

「瀬戸内のつくり手たちと出会うイベントづくりワークショップ」を開催します!
2025.07.17
- 施設サポーターのコメント
- 仕事柄、これまで多くの地域で暮らしてきましたが、その中で意識してきたのは、地域の習わしや習慣、地元食材やイベント、観光名所に至るまで、その土地ならではの文化に積極的に触れ、それらを生活に取り込み、そして楽しむことでした。
仕事やプライベートに関わらず、その地域とどれだけ触れ合うことができるか。それこそ、その土地で生まれ育ったかの如く、そこでの暮らしが自然と思えるほど身近に感じられるようになることが、地域との深く良好な関係性に繋がるのではないかと思います。
せっかく縁あってその土地で暮らすことになったのならば、さまざまな場所に積極的に飛び込み、地域を味わい尽くす。
地域と触れ合う機会を主体的につくり出していくことが、地域との関わりを築く第一歩になるはずです。
参加者の皆さんにとって今回のイベントが、地域との関わりを「つくる」良いきっかけになることを願っています。

山瀬 功治
レノファ山口FC クラブ・コミュニティ・コネクター

コミュニケーションには、何が必要だと思いますか?<KDDI維新ホール山口ミライ共創ラボ5月10日イベントレポート>
2025.06.06
- 施設サポーターのコメント
- 5/10の本イベントではありがとうございました。とても濃密で有意義な時間を過ごすことができました。トークセッションではパネリストの方々から同世代や、遠くにいる仲間とのコミュニケーションの課題意識を伺えました。そして既に皆様は自分なりの解決方法を模索されていました。今後開催のワークショップでは、「インプロ的視点」から、課題解決のためのヒントを提供したいと思います。
インプロショーは、とても明るく良い雰囲気の中で行えました。急遽ショーに参加していただいた観客の方々の堂々たる演技には、正直びっくりしました。
これからのワークショップがとても楽しみです。皆様、よろしくお願いします。

谷本 正志
インプロファシリテーター
.jpg)
【なぜ私たちは「まつり」を継承するのか】山口大学*風土と感性プロジェクト
2025.06.05
- 施設サポーターのコメント
- 「なぜ私たちはまつりを継承するのか?」
まつりとは、地域社会の暮らしの中で信仰を基盤に営まれてきた、人々の主体的な行為や言葉の積み重ねを指します。地域を深く理解するためには、その土地が長年にわたり受け継いできた「暮らしの文化」に着目することが欠かせません。しかし、文化は形として明確に存在するものではなく、その存在をいかに可視化していくかが重要な課題となっています。
「風土と感性」プロジェクトでは、山口市で行われている5つのまつりを対象にフィールドリサーチを実施し、大学生の視点からまつりの持続可能性に関する12の提言をまとめました。これらの取り組みは、山口の文化を理解する手がかりとなるだけでなく、若い世代が地域の価値を再発見し、未来へとつなぐ創造的な対話の出発点にもなっています。

坂口 和敏
山口大学 大学院人間社会科学研究科・国際総合科学部 准教授
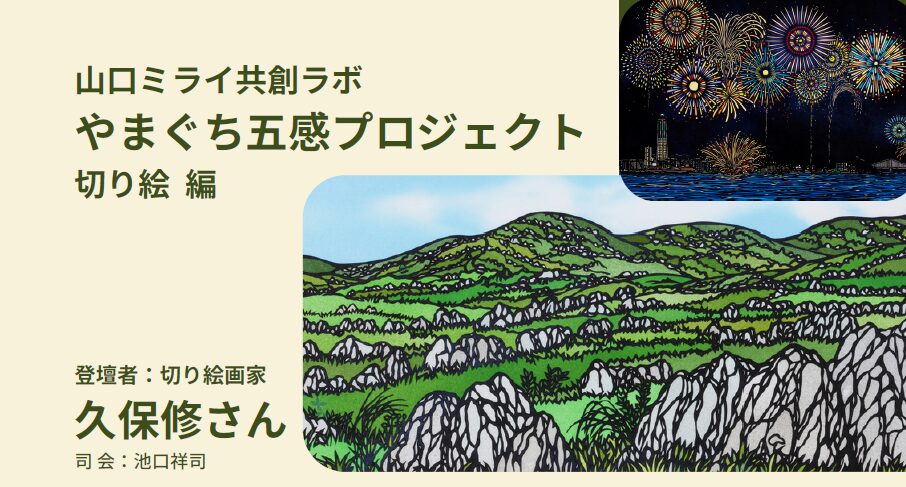
『切り絵画家・久保修さんの軌跡~巨匠との出会い・震災の経験が生んだ表現の進化~』切り絵にも初挑戦しました!
2025.06.04
- 施設サポーターのコメント
- この記事では、山口県美祢市出身の切り絵画家・久保修さんの歩みと、彼の作品に込められた想いが紹介されています。久保さんは、岡本太郎氏の厳しい助言や阪神・淡路大震災の経験を通じて、切り絵の表現を深化させてきました。地域の風景や食材を題材にした彼の作品は、その土地の魅力を再発見させてくれます。
イベントに参加し、記事を執筆した大学生は、切り絵体験を通じて地域の文化や自然への理解が深まったと感じています。
「ココロが動く」──この活動には、地域活性化の一助となる大きな可能性を感じました。
.jpg)
村田 純司
KDDI維新ホール ディレクター

「インプロ」(即興演劇)体験が自分を変える!?体と脳を活性化するインプロの魅力【KDDI維新ホール 山口ミライ共創ラボ特別インタビュー】
2025.05.30
- 施設サポーターのコメント
- 演劇と聞くとあらかじめストーリーが決められており、演出家や出演者を通した解釈が舞台上で繰り広げられる様子を想像する人が多いと思います。
このインプロと呼ばれる即興演劇は、その場で出会う出演者たちが即興でシーンや物語を作っていく、一度きりの予測不能な展開が面白い。
さらには単なる娯楽としてではなく、企業の研修やコミュニケーション能力の向上にも役立つという。改めて考えてみると我々が過ごしている日常も舞台上という非日常ではないものの、即興の連続である。
山口市産業交流の拠点で開催されるインプロが参加者にどういった影響を与え、波及していくのか、能力開発や人材育成という視点でも面白い取り組みだと感じます。

新造 太郎
SSSグループ

一の坂川を中心に読み解く、山口の人間と自然の世界
2025.05.30
- 施設サポーターのコメント
- 「川とともに生きる地域の生態系」
川には、上流から下流に至るまで、さまざまな表情があります。
地域の生態系において、川は重要なインフラストラクチャーとして機能し、四季折々の資源を地域全体で共有しています。私たちが普段目にしているのは、中流から下流にかけての川の姿がほとんどです。川は、そこで暮らす人々の食文化や芸術など、多様な文化の形成にも大きな影響を与えてきました。しかし近年では、治水工事によって人工的に整備された川を目にすることが多くなり、本来の川の姿が見えにくくなっています。けれども、中流から上流へと遡ると、いまなお息づく生態系の豊かさに触れ、かつて人と自然が紡いできたつながりを思い起こすことができるでしょう。

坂口 和敏
山口大学 大学院人間社会科学研究科・国際総合科学部 准教授
.jpg)
自然と「生」の循環~多元世界から~《風土と感性プロジェクト フィールドワークレポート》
2025.05.30
- 施設サポーターのコメント
- 「山と風土から読み解く多文化理解」
「西の京」と呼ばれる山口は、周囲を山地に囲まれた盆地に位置しています。
そのため、まちの至るところで山の姿を目にすることができます。標高がそれほど高くない山々が連なるのが特徴で、雨上がりには山肌から水蒸気が立ち上り、自然の息吹が感じさせる独特な景観を生み出しています。このような風景は、雪舟の水墨画にも数多く描かれています。姫山は、山口大学のほど近くにあり、大学祭の名称にもその名が使われています。山が地域に与える影響を探ることで、私たちの暮らしを見守り続けてきた地域の風土に、改めて思いを馳せることができるでしょう。

坂口 和敏
山口大学 大学院人間社会科学研究科・国際総合科学部 准教授
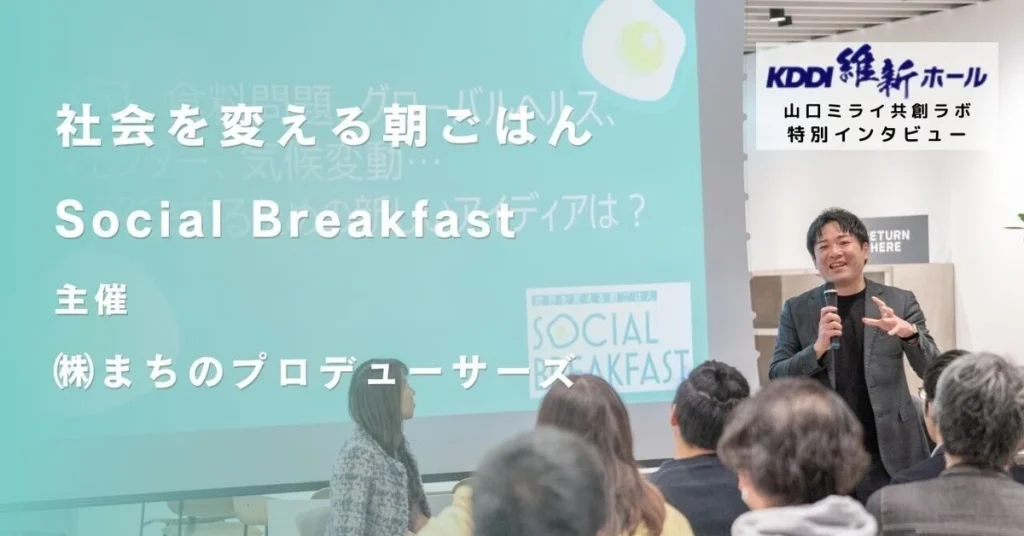
社会を変える朝ごはんSocial Breakfast主催㈱まちのプロデューサーズ≪山口ミライ共創ラボ特別インタビュー≫
2025.05.30
- 施設サポーターのコメント
- 朝ごはんをきっかけに社会課題を考えるという発想がとてもユニークで、共感しました。そして、地元山口市で「Social Breakfast」が開催されていると知り、地域が全国とつながっているようでとても心強く感じました。私も日々お客様と接する中で、地域の課題や声に触れる機会が多くあります。「Social Breakfast」のように気軽に集える場があることで、社会に向けて一歩踏み出す人が増えるのではと感じております。

原田 紗弥
三角チーズサンドパン専門店

人工物からの離脱:熊野神社で感じた自然の力≪風土と感性プロジェクト フィールドワークレポート≫
2025.05.30
- 施設サポーターのコメント
- 「神社と地形が語る地域の風土」
私たちの祖先は、なぜその場所に神社を建てることを選んだのでしょうか。
神社は、地域を守る氏神を祀る存在です。数ある選択肢の中で、なぜその場所が選ばれたかを読み解くことは、風土が持つ地形的特性を知る手がかりとなります。熊野神社は、開けた山口盆地の中で、地域を一望できる高台に位置し、遠くからでもその存在を感じることができます。人々はこの丘に愛着を抱き、その象徴として神社を建立したのではないでしょうか。こうした視点から神社と土地との関係を捉え直すことで、風土に根ざした暮らしの知恵を未来へと引き継ぐ手がかりが得られるでしょう。

坂口 和敏
山口大学 大学院人間社会科学研究科・国際総合科学部 准教授

世界にアーモンドの種をまき続ける 音楽活動家・松田亜有子さんが語るクラシック音楽のもつユニバ―サリティ ―芸術・風土・感性を考える―
2025.05.30
- 施設サポーターのコメント
- 私自身、日々の生活に追われ、目の前のことばかりを優先してしまうことが多い日常を過ごしていますが、やまぐち五感プロジェクトに参加して、私たちの生活の中で、「五感」や「感性」にフォーカスすることの大切さを思い出したところです。
今回のnoteを読み、久しぶりに、ピアノの音に耳を傾けたり、鍵盤に触れる感触を楽しみたくなりました。素晴らしい記事をありがとうございました。
私は山口市職員として、KDDI維新ホールの業務に携わっています。やまぐち五感プロジェクトを始め、山口ミライ共創ラボなど、KDDI維新ホールでの企画事業に、大学生だけでなく、幅広い世代の方、地域内外の多くの方々に参加していただき、関係性を広げ、深めていきたいと思っています。そこから何か新しいものが生み出される契機となることを願いながら!
自分の「感性」が少しでも動くものがあれば、気軽に参加してみてください!KDDI維新ホールで皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。

田邊 京子
山口市商工振興部 ふるさと産業振興課 起業創業支援担当 主幹

地域との関わり方を考える ―「わたしと地域の関係性 #2」イベントレポート
2025.05.30
- 施設サポーターのコメント
- 記事中の「一番大切なのは、まずはやってみること」と「その地域に住んでいて生きているだけで、関係性は築けている」に、とても共感しました。
私はこれまでずっと東京都内でインプロ(即興演劇)ワークショップを開催していました。ただ住まいのある松戸市では活動を行っていなかったため、昨年「IMPRO JOBANS」というグループを立ち上げて活動を開始しました。その後、多くのご縁をいただき幸運にも、市内で開催されたイベントでインプロショーの舞台に立つことができました。また会場では、直接の知人や、知人の知人にも出会えました。
まずはやってみることの大切さ、そして地域での関係性を認識できた貴重な経験でした。

谷本 正志
インプロファシリテーター

会社員として移住し、地域を耕す―「わたしと地域の関係性 #3」イベントレポート
2025.05.30
- 施設サポーターのコメント
- タイトルにもなっている「地域を耕す」という言葉にとても共感しました。地域創生や地域活性化は、何かをして終わりではなく、未来に向けてずっと続いていく何かを同じ想いを持った仲間と育てていくことなんだなと思います。
黒木さんが長門という土地に新しい風をおこされることで、今までにない素敵なモノやコト、そして繋がりが生まれていくことにとても期待しています!

伊藤 啓子
UNDERSCOREBASE株式会社(名田島食堂)

